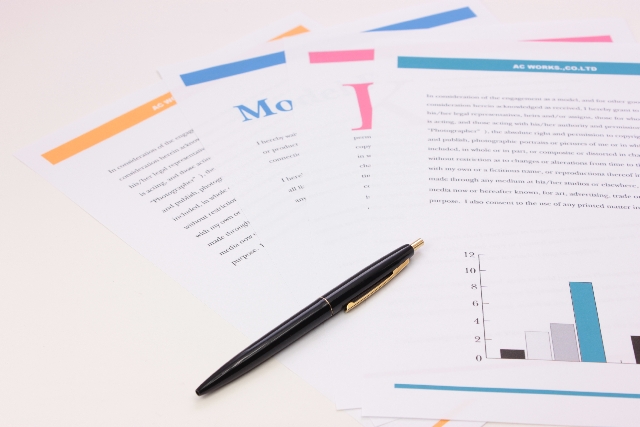


年金の不払いなどについて質問です、無知ですみません
私は2012年の4月にある企業に入社し2ヶ月後の6月に辞めてしまいました。
その後はバイトを始めて、保険は親に扶養してもらったのですが、退職したあとの公的な手続きがわからず、年金など色々なものをほったらかしにしてきました。
退職したあとは何か公的な手続きが必要だったのでしょうか?
もし、よければその公的な手続きを詳細に書いていただけ無いでしょうか?
よろしくお願いします。
私は2012年の4月にある企業に入社し2ヶ月後の6月に辞めてしまいました。
その後はバイトを始めて、保険は親に扶養してもらったのですが、退職したあとの公的な手続きがわからず、年金など色々なものをほったらかしにしてきました。
退職したあとは何か公的な手続きが必要だったのでしょうか?
もし、よければその公的な手続きを詳細に書いていただけ無いでしょうか?
よろしくお願いします。
基本的に必要な公的手続きは、雇用保険(失業給付)、国民年金、国民健康保険の3つです。
まずは雇用保険(失業給付)からです。
この手続きは、住居地を管轄するハローワークで行います。
退職した会社から「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を受け取ってからにハローワークに行き、失業給付金を受け取る手続きを行います。
手続きには以下のものが必要です。
・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・雇用保険被保険者証
(自分で保管していない場合は、会社から退職当日に渡されます)
・官公署の発行した写真つき身分証明書
(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
・写真2枚
(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの)
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳
(ここに給付金が振り込まれます)
次に国民年金、国民健康保険の手続きです。
この手続きは、居住地管轄の市町村役所・役場の担当窓口で行います。
退職後14日以内に手続きするのが基本になっています。
国民年金の手続きには以下のものが必要です。
・年金手帳
(自分で保管していない場合は、会社から退職当日に渡されます)
・官公署の発行した身分証明書
(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
・印鑑
※14日を過ぎてしまっても問題はありませんが、なるべく早く手続きをしましょう。国民年金の支払期限は2年です。これを過ぎると保険料を払うことができなくなります
国民健康保険の手続きには以下のものが必要です。
・退職した会社発行の健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれか
(離職票はハローワークに提出するので、その前に手続きする)
・官公署の発行した身分証明書
(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
・印鑑
こちらも14日を過ぎてしまっても問題はありませんが、なるべく早く手続きをしましょう。なお、遅れて手続きをしても、会社の健康保険を抜けた翌月分から徴収されます。
※健康保険に関しては、国民健康保険に加入する以外に、以下の選択肢もあります。場合によっては検討しても良いと思います。
・今まで加入していた健康保険の任意継続被保険者になる
(継続して2か月以上の被保険者期間があり、資格喪失日から「20日以内」に申請)
・収入が少なく、かつ家族が働いている場合、その家族の被扶養者になる
どれも基本的な内容でしたが、初めて手続きする貴方さまの参考になればと思います。
補足を読んで・・・
質問者様の言われるとおり、雇用保険の受給資格を得るには、基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要です。雇用保険適用の複数の会社で働いたことがある場合、働いた期間の合計が1年以上あれば条件を満たします。
その他、会社の倒産などやむを得ない事業で失業した場合などは「短期雇用特例被保険者」という扱いになって、期間の条件が6ヶ月に短縮される制度があります。
なので、この場合は「国民年金」手続きだけを行えばいいようですね。
あと、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときには、未納のままにしないで「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行うことをお勧めします。
この制度を利用すると、保険料免除や納付猶予になった期間も、年金の受給資格期間(25年間)に算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
・保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
・保険料納付猶予制度とは
20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを若年者納付猶予制度といいます。
●手続きをするメリット
・保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをしていただけず、未納となった場合1/2(税金分)は受け取れません。)
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料免除・納付猶予の種類と審査方法
・パート・アルバイト等で厚生年金に加入していない方
(保険料免除制度)ご本人・世帯主・配偶者 各々の所得審査
(若年者納付猶予制度)ご本人・配偶者 各々の所得審査
・会社を退職した方
(失業による特例免除)世帯主・配偶者 各々の所得審査
・学生の方
(学生納付特例制度)ご本人の所得審査
まずは雇用保険(失業給付)からです。
この手続きは、住居地を管轄するハローワークで行います。
退職した会社から「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を受け取ってからにハローワークに行き、失業給付金を受け取る手続きを行います。
手続きには以下のものが必要です。
・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・雇用保険被保険者証
(自分で保管していない場合は、会社から退職当日に渡されます)
・官公署の発行した写真つき身分証明書
(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
・写真2枚
(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの)
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳
(ここに給付金が振り込まれます)
次に国民年金、国民健康保険の手続きです。
この手続きは、居住地管轄の市町村役所・役場の担当窓口で行います。
退職後14日以内に手続きするのが基本になっています。
国民年金の手続きには以下のものが必要です。
・年金手帳
(自分で保管していない場合は、会社から退職当日に渡されます)
・官公署の発行した身分証明書
(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
・印鑑
※14日を過ぎてしまっても問題はありませんが、なるべく早く手続きをしましょう。国民年金の支払期限は2年です。これを過ぎると保険料を払うことができなくなります
国民健康保険の手続きには以下のものが必要です。
・退職した会社発行の健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれか
(離職票はハローワークに提出するので、その前に手続きする)
・官公署の発行した身分証明書
(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
・印鑑
こちらも14日を過ぎてしまっても問題はありませんが、なるべく早く手続きをしましょう。なお、遅れて手続きをしても、会社の健康保険を抜けた翌月分から徴収されます。
※健康保険に関しては、国民健康保険に加入する以外に、以下の選択肢もあります。場合によっては検討しても良いと思います。
・今まで加入していた健康保険の任意継続被保険者になる
(継続して2か月以上の被保険者期間があり、資格喪失日から「20日以内」に申請)
・収入が少なく、かつ家族が働いている場合、その家族の被扶養者になる
どれも基本的な内容でしたが、初めて手続きする貴方さまの参考になればと思います。
補足を読んで・・・
質問者様の言われるとおり、雇用保険の受給資格を得るには、基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要です。雇用保険適用の複数の会社で働いたことがある場合、働いた期間の合計が1年以上あれば条件を満たします。
その他、会社の倒産などやむを得ない事業で失業した場合などは「短期雇用特例被保険者」という扱いになって、期間の条件が6ヶ月に短縮される制度があります。
なので、この場合は「国民年金」手続きだけを行えばいいようですね。
あと、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときには、未納のままにしないで「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行うことをお勧めします。
この制度を利用すると、保険料免除や納付猶予になった期間も、年金の受給資格期間(25年間)に算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
・保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
・保険料納付猶予制度とは
20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを若年者納付猶予制度といいます。
●手続きをするメリット
・保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをしていただけず、未納となった場合1/2(税金分)は受け取れません。)
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料免除・納付猶予の種類と審査方法
・パート・アルバイト等で厚生年金に加入していない方
(保険料免除制度)ご本人・世帯主・配偶者 各々の所得審査
(若年者納付猶予制度)ご本人・配偶者 各々の所得審査
・会社を退職した方
(失業による特例免除)世帯主・配偶者 各々の所得審査
・学生の方
(学生納付特例制度)ご本人の所得審査
以前、応募した企業に別職種でまた応募可能でしょうか?
2月にハローワークから税理士法人に税務会計業務(正社員)で応募しましたが、不採用になりました。
今週発行の求人誌にまた掲載されていました。
今度は、会計データ入力業務(パート)で応募したいのですが、可能でしょうか?
パソコンデータ入力は
●一般・経理事務経験者尚可
●日商簿記2級以上尚可
と記載されています。
私(男)は、上記の資格(日商簿記2級)を持ってますし、7年前に税務会計業務を7年経験しております。
履歴書(写真添付)を郵送下さい。後日、試験・面接日を連絡致します。と記載されていますが、
電話をして一度確認した方が良いでしょうか?
どうか、ご教授願います。
※7年前にやっていた仕事は、他に、10種類以上の共済推進、各種団体事務委託、パソコン講習会、珠算検定、簿記講習会、講演会の開催、各種部会、町のお祭の企画実行(主担当)で体調を害して辞めた為、今一度附随的ですが税務会計に携わりたいのです。
※昨年の11月で介護の仕事を退職後、どこの企業に応募しても不採用で無職です。
ブランクがあり不安もありますが、体調体力的には何ら問題ありません。
2月にハローワークから税理士法人に税務会計業務(正社員)で応募しましたが、不採用になりました。
今週発行の求人誌にまた掲載されていました。
今度は、会計データ入力業務(パート)で応募したいのですが、可能でしょうか?
パソコンデータ入力は
●一般・経理事務経験者尚可
●日商簿記2級以上尚可
と記載されています。
私(男)は、上記の資格(日商簿記2級)を持ってますし、7年前に税務会計業務を7年経験しております。
履歴書(写真添付)を郵送下さい。後日、試験・面接日を連絡致します。と記載されていますが、
電話をして一度確認した方が良いでしょうか?
どうか、ご教授願います。
※7年前にやっていた仕事は、他に、10種類以上の共済推進、各種団体事務委託、パソコン講習会、珠算検定、簿記講習会、講演会の開催、各種部会、町のお祭の企画実行(主担当)で体調を害して辞めた為、今一度附随的ですが税務会計に携わりたいのです。
※昨年の11月で介護の仕事を退職後、どこの企業に応募しても不採用で無職です。
ブランクがあり不安もありますが、体調体力的には何ら問題ありません。
○2月にハローワークから税理士法人に税務会計業務(正社員)で応募しましたが、不採用になりました。今度は、会計データ入力業務(パート)で応募したいのですが、可能でしょうか?
>応募すること自体は問題ありません。
ご質問者様は、税務会計の経験もあり、この職種への就業を希望されていらっしゃいますが、2月の採用試験で能力や適正、その他で不採用とされたのでしょうから、パートのデータ入力業務でも結果は同じなのでは?
そもそも、会計データ入力業務(パート)は男性が担当する仕事でしょうか?
多くの場合は、女性の方が庶務的な業務を兼ねて担当しているのでは?
>応募すること自体は問題ありません。
ご質問者様は、税務会計の経験もあり、この職種への就業を希望されていらっしゃいますが、2月の採用試験で能力や適正、その他で不採用とされたのでしょうから、パートのデータ入力業務でも結果は同じなのでは?
そもそも、会計データ入力業務(パート)は男性が担当する仕事でしょうか?
多くの場合は、女性の方が庶務的な業務を兼ねて担当しているのでは?
ご存じの方教えてください。。【失業保険】受給中、ハローワークの紹介で『季節臨時』で働いています.6カ月臨時で今月で契約、終了します..残りの【失業保険】は受給できますが、臨時で働い雇用保険は、適用しな
いのでしょうか?
いのでしょうか?
受給の際、職安の方に尋ねてみてはいかがでしょうか?
自分も以前、失業保険を受給してました。
受給の際に職安に提出する用紙がありますよね?
それを持って職安の方に尋ねてみてはいかがでしょうか?
臨時だと・・・・トライアルみたいなものだから、適用されなかったはず。
やはり、職安の方に尋ねてみて下さい
自分も以前、失業保険を受給してました。
受給の際に職安に提出する用紙がありますよね?
それを持って職安の方に尋ねてみてはいかがでしょうか?
臨時だと・・・・トライアルみたいなものだから、適用されなかったはず。
やはり、職安の方に尋ねてみて下さい
関連する情報